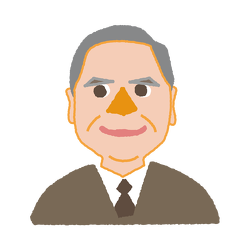第5回:糖尿病について<後編>(糖尿病と血糖コントロールの重要性)
今回は、「糖尿病と血糖コントロールの重要性」についてご紹介します。肥満、メタボの方も大いに関係しますので、ぜひお読みください。
血糖値調節が崩れる原因(2型糖尿病の発病)
第4回コラムで、体内には血糖値調節のしくみがあり、血糖値は通常70~140mg/dlの範囲にコントロールされていることを説明しましたが、肥満、ストレス、運動不足、過食、老化、妊娠、遺伝的要因などのリスク要因が生じると、膵臓の疲弊、老化によるインスリン分泌低下や肥満増加、筋肉量減少によるインスリンへの感受性の低下をきたし、慢性的に高血糖が継続する糖尿病へと進行します。
膵臓のインスリンを作る細胞は僅か0.9グラムしかないそうです。酷使するとすぐに疲れそうですね。
糖尿病の原因と発症(2型糖尿病の場合)
様々な原因
肥満、運動不足、過食、妊娠、遺伝的要因、廊下、ストレス等
↓
膵臓の疲弊、老化によるインスリン分泌低下
肥満増加、筋肉量減少によるインスリンへの感受性低下
↓
インスリン作用の低下
↓
高血糖の継続化
↓
糖尿病発症

糖尿病はなぜ怖いのか?
糖尿病そのものは自覚症状があまりないのですが、高血糖が続くと下記のような恐ろしい合併症を引き起こし、生活の質が低下し、寿命にも影響します。
慢性合併症の発症メカニズムですが、糖尿病により高血糖が続くと、ブドウ糖が血管や末梢神経を傷つけることにより合併症を引き起こします。
<急性>
糖尿病性ケトアシドーシス
1型の若年者で多い。重度では意識障害、昏睡を生じる。
高浸透圧高血糖
2型の高齢者で多い。重度では意識障害、昏睡を生じる。
<慢性>
・細い血管の障害によるもの(三大疾病)
糖尿病性網膜症
眼底にある網膜が剥離し最悪は失明に至る。
糖尿病性腎炎
腎臓のろ過能力が低下、最悪は人工透析が必要となる。
糖尿病性神経障害
自律神経、末梢神経の壊死、進行すると手足の壊疽(腐る)を引き起こす。
・太い血管の障害によるもの
高血圧、脳梗塞・脳出血、心筋梗塞、免疫機能の低下、歯周病、認知症、がん など
糖尿病の治療(血糖コントロール)
糖尿病を発症しても合併症を起こさない、進行させないなら、健常人と同じような生活を送ることができます。そのためには、できるだけ早期から、低血糖に留意しながら(特に高齢者)、高すぎる血糖値を適切なレベルに下げること(血糖コントロール)が必要です。
具体的には、医師が患者の年齢、合併症などの状況に応じた「血糖コントロールの目標値(例えばHbA1c)」と以下の3つの治療方法などを設定し、進められます。
- 食事療法
摂取カロリーを考慮し、栄養バランスの取れた食事を規則正しく摂ることが推奨されています。なお、近年、糖質制限食という比較的新しい食事療法が取り入れられるケースがあります。
- 運動療法
運動により糖、脂肪が消費されます。また、運動による内臓脂肪の減少や筋肉量の増加により、インスリンの効き目が良くなる効果があります。
- 薬物療法
2型糖尿病においては、「食事療法」及び「運動療法」の対策で十分に血糖コントロールができない場合、薬物による治療が必要となります。飲み薬と注射薬があります。インスリン注射は、1型の人や2型で飲み薬での効果が不良の方に用いられています。

HbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)について
HbA1cは赤血球中に含まれるへモグロビンがブドウ糖と結合したもの。
ヘモグロビン全体に占めるHbA1cの割合(%)で示します。HbA1cの値が血糖値に比例することから用いられています。赤血球の寿命は約120日ですが、毎日入れ替わっていて新しいものと古いものが混ざっていることから過去1~2ヶ月の血糖値の平均値を示します。
以下に、薬局勤務の経験をもとに糖尿病薬の利用時などでの留意点を記載しました。参考にして下さい。
- 低血糖は、低血糖を起こしやすい糖尿病薬(SU剤、グルニド薬、インスリン注射など)を服用している時、高齢者の方が糖尿病薬の服用中に高熱や腹痛などで食事がとれない時(「シックデイ」と呼ぶ)、運動中に起こりやすいので注意が必要です。
- インスリン注射の保管温度は冷蔵と認識されていると思いますが、開封後の保管温度(室温など)、使用期限は別途設定されているものがありますので説明書をご確認ください。
- 糖尿病を発症しても眼科は受診されない方が多数いらっしゃいます。症状が出てからでは手遅れになる場合があります。眼科を受診しましょう。
- 自己血糖測定器を使用すると、自身で血糖コントロールの効果をチェックできたり、低血糖の防止にも繋がります。操作は簡単です。保険適用にならない場合でも、取り扱いのある薬局等で購入できます。
最後に
健康診断で要再検査などの結果を受けている方、すでに体に変化が生じている可能性があります。手遅れになる前に必ず検査を受けて下さい。また肥満やメタボの方は糖尿病の発症リスクをお持ちですので、この機会にダイエットを始めてみて下さい。
参考資料:
・鈴木吉彦. よくわかる最新医学 糖尿病 最新治療・最新薬, 株式会社主婦の友社, 平成26年.
・山田悟, 忙しい人こそ知っておきたい糖尿病がわかる本, 株式会社法研, 平成26年.